日本のウイスキーは世界中で高い評価を受けていますが、その「ジャパニーズウイスキー」という呼称には明確な基準が存在しませんでした。
その結果、日本産以外の原酒を使った製品までが「ジャパニーズ」を名乗り、消費者が混乱する事態も発生していました。
2021年に日本洋酒酒造組合が中心となり、ジャパニーズウイスキーを名乗るための定義が制定。
2024年より施行されることとなりました。
本記事では、その定義の具体的な内容や背景、そしてサントリーやニッカといった代表銘柄との関係を詳しく解説します。
正しい知識を持つことで、購入時に迷わず本物を選ぶ力が身につき、友人や仲間との会話にも自信を持って臨めるようになるでしょう。
ジャパニーズウイスキーとは

ジャパニーズウイスキーといえば日本で作られたウイスキーのことだと思いますが、現在でも実際には法的な効力は酒税法で定義されている「ウイスキー」の範囲しか持っていません。
第三条(用語の定義)
十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
- イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が 九十五度未満のものに限る。) - ロ 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が 九十五度未満のものに限る。) - ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量が、アルコール・スピリッツ・香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の 百分の十以上のものに限る。)
簡単にまとめると……
ウイスキーは基本的に 発芽させた穀類(=モルトなど)と水を用い、糖化 → 発酵 → 蒸留 して造られていることが大前提。
そして、蒸留時のアルコール分は 95度未満であることが条件となっております。
そして上の2つを満たした「ウイスキー」をベースにしたものへ アルコールやスピリッツ、香味料等を加えることも可。
アルコールやスピリッツ、香味料などを添加しても「ウイスキー」に含まれますが、必ず ベースのウイスキー由来のアルコールが10%以上を占める必要があります。
逆を言えば、「ウイスキー」と呼べるものが10%以上含まれていれば、日本では「ウイスキー」と名乗れるのです。
ジャパニーズウイスキーの基本的な定義
世界5大ウイスキーに数えられてもなお、10%程度しかウイスキーが含まれていなくてもウイスキーと呼べてしまう日本。
その現状を問題視した日本洋酒酒造組合が、2021年に「ジャパニーズウイスキー」を自主基準によって明確化しました。
| 特定の用語 | 製法品質の要件 |
|---|---|
| 原材料 | 原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。 なお、麦芽は必ず使用しなければならない。 |
| 製法 製造 | 糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。 なお、蒸留の際の留出時のアルコール分は95度未満とする。 |
| 貯蔵 | 内容量700リットル以下の木製樽に詰め、当詰めた日の翌日から起算して3年以上日本国内において貯蔵すること。 |
| 瓶詰 | 日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は40度以上であること。 |
| その他 | 色調の微調整のためのカラメルの使用を認める。 |
スコッチウイスキーの定義がベースとなっておりますが、ジャパニーズウイスキー独自の決まりもあります。
自主基準に関する経緯や影響、スコッチウイスキーとの違いは下で解説させていただきます。
ジャパニーズウイスキーの特徴

従来のジャパニーズウイスキーは、「自由度」と職人気質が最大の特徴だったといえるかもしれません。
明確な定義がなかったため、日本人ならではの勤勉さ・職人気質から自由な発想のウイスキーが生まれていきました。
その最たる銘柄が「角瓶」や「ブラックニッカ」シリーズだと思います。
日本人の舌に合わせつつも、ウイスキーらしい奥深さ・芳醇さを兼ねそろえた絶妙なバランス。
もし最初から厳格にジャパニーズウイスキーが定義されていたとしたら、このようなウイスキーは生まれなかったかもしれません
ところが、明確な定義がないからこそジャパニーズウイスキーは「イミテーション」の歴史でもあります。
いまだにその風潮が残っており、中には10%程度しか「ウイスキー」と呼べる原酒が含まれていない銘柄も。
スコッチやアイリッシュと比較してバランス・調和と繊細さに優れた銘柄が多いです。
しかし、自主基準が設けられた法的な効力が少なく、今でも「イミテーション」ウイスキーがいまだにある良くも悪くも自由なウイスキーが今もジャパニーズウイスキーです。
日本におけるウイスキー造りの起源
日本のウイスキーづくりは、1920年代に竹鶴政孝がスコットランドで学んだウイスキー製造の技術と理念を日本に持ち帰ったことから始まりました。
彼は本場で得た知識をもとに、日本の気候・水・原料に合わせた製造法を研究し、日本独自のウイスキーづくりを模索します。
その後、寿屋(現サントリー)が竹鶴を招き入れ、1923年に日本初の本格蒸溜所「山崎蒸溜所」を大阪府に建設。
ここで生まれたウイスキーは、日本の風土と職人技を融合させた新しい酒文化の幕開けとなりました。
以降、日本のウイスキーは改良と革新を重ね、世界に誇る品質を築くまでに発展していきます。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1918年 | 竹鶴政孝がスコットランドに留学し、ウイスキー製造を学ぶ |
| 1923年 | サントリー(当時寿屋)が日本初の本格蒸溜所「山崎蒸溜所」を設立 |
| 1934年 | 竹鶴政孝が北海道に「余市蒸溜所」を設立、ニッカウヰスキー創業 |
| 1937年 | サントリー「角瓶」発売、日本のブレンデッドウイスキー文化が広がる |
| 1984年 | サントリー「山崎12年」発売、ジャパニーズウイスキーが世界に進出 |
| 2001年 | 「ニッカ余市10年」世界的品評会で金賞受賞、日本ウイスキーが国際的評価を獲得 |
| 2021年 | 日本洋酒酒造組合が「ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定 |
| 2024年 | 基準の経過措置が終了し、正式に適用開始 |
重要なブランドの登場
その後、サントリーの「角瓶」やニッカウヰスキーの「ブラックニッカ」などが登場し、日本のウイスキー市場を拡大。
さらに山崎や白州、余市、宮城峡などのシングルモルトが世界的評価を受け、ジャパニーズウイスキーは国際的ブランドへと成長しました。
ジャパニーズウイスキーの厳格化

なぜ定義が厳格化されているのか
背景は、海外市場で「日本産ではない」原酒を使用した製品がジャパニーズウイスキーと称して販売され、消費者の混乱を招く結果を生んでいたことです。
日本には酒税法による規定はありますが、スコッチウイスキーのような法的な定義がありません。
さらに原産国である日本では、90%近くがスピリッツでも「ウイスキー」と名乗れてしまいます。
ジャパニーズウイスキーが世界的に評価されてからなお、偽物が横行してしまうこととなってしまいました。
- 原産国である日本に明確な「ジャパニーズウイスキー」の定義がない
- 熟成年数の縛りがなく、熟成してない原酒を混ぜても「ウイスキー」と名乗れる
- 1割程度「ウイスキー」が混ざっていれば、「ウイスキー」と名乗れる
国内でも国産ウイスキーの需要や関心が高まった結果、この穴をついて怪しい「ウイスキー」が市場に出回ってしまっています。
こうした問題を防ぎ、国内外の信頼を守るため、明確な基準が制定されました。
新しい基準の内容と影響
基準は2021年4月に施行され、2024年3月までの経過措置を経て完全適用されます。
この定義により、純粋に「日本で造られた」ウイスキーだけがジャパニーズウイスキーを名乗れるようになりました。
現在では、主要メーカーをはじめ製品のラベルやブランドページなどに「日本洋酒酒造組合の定めるジャパニーズウイスキーの表示基準に合致した商品です」と記載がされています。
ところが、いまだに法的な効力ないため、基準を満たしていない銘柄が単に「ウイスキー」として販売することは可能。
また、この規定の影響で、直近のジャパニーズウイスキーの輸出は減ると見込まれています。
世界的な評価、地位を今より高めるために、変化が必要な時期になったのかもしれません。
スコッチウイスキーの定義との違い
ジャパニーズウイスキーの自主基準は、スコッチウイスキーの定義に沿ったものとなっておりますが、やや厳しいものとなっています。
スコッチウイスキーの定義との大きな違いは、下記の3つです。
- 日本の水を使用しないといけないこと
- 樽の指定がないこと
- 日本国内で瓶詰めまで行うこと
スコッチはシングルモルト以外、海外で瓶詰めしても「スコッチ」と名乗れるのに対し、ジャパニーズウイスキーは瓶詰めまで国内で行うことが必要。
また水も日本のものを使用することが定められています。
これは、バルクウイスキーという大容量で輸出して海外でブレンドすることを禁止するための規定となっています。
また、熟成樽の材質についてスコッチはオークに限定されますが、日本では桜や杉など多様な木材の可能性を残している点も特徴です。
ジャパニーズウイスキーの未来
今後のトレンドと市場の動向
近年、ジャパニーズウイスキーの需要が高まり、価格が高騰。
ウイスキー愛好家だけでなく、投資目的でウイスキーの限定品や長期熟成品を購入する方が多く入手困難な状態となっていました。
一方で、クラフト蒸溜所の新設が相次ぎ、2000年以前には10件未満しかなかった日本のウイスキー蒸留所は、2025年現在では計画中も含めて120件を超える勢いとなっております。
国産ウイスキーの輸出額は2022年に約560億円で過去最高を記録しました。
ところが、2022年以降は年々輸出額が減少。
投資としてのウイスキーの注目度が下がっており、日本のウイスキーブームも落ち着きつつある状況です。
また、自主基準が海外にも認知され始めたら、一時的に輸出額も下がるでしょう。
ブームが落ち着きつつある今だからこそ、ジャパニーズウイスキーは新たな転換点となっているのかもしれません。
新しい銘柄やリリースの検討
若い蒸溜所からリリースされる新作や、桜樽・栗樽といった独自の熟成方法を用いた製品が今後のトレンドとなるでしょう。
実際に山鹿蒸留所や新道蒸留所の製品には、栗樽熟成の原酒が使われているものもあります。
これらは日本独自の自然環境と文化を反映した、新しいジャパニーズウイスキーの姿を示しています。
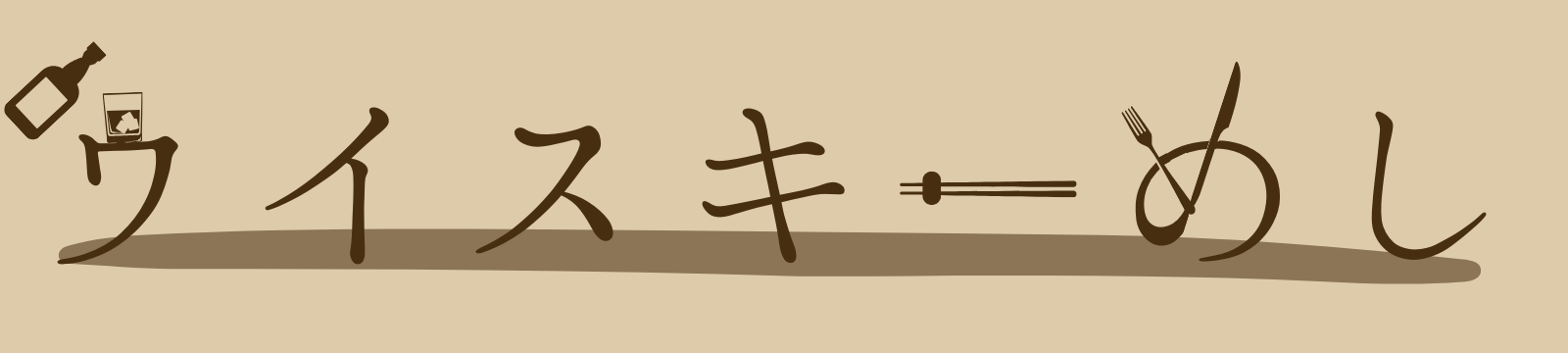


コメント